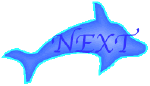(テキスト作成は1997年)
第27話 大西洋 陽はまた昇る
脚本・松岡清治 絵コンテ・斧谷稔
119◆海神トリトン◆
大小の魚の大群、そしてイルカの群れ、その中心にトリトンがいた。ポセイドンの神殿へ突入した魚たちは、通信クラゲ、マーカス、ゲルペス連隊へ襲いかかる。魚たちは狂ったわけではない。トリトンに先導され鼓舞されて闘っているのだ。田中光二「怒りの大洋」の如きこの場面は、トリトンが魚たちの中から引き出したものなのである。
このような、今まで無抵抗だったものが、突如として決起し、雪崩をうって反抗する。映画「アルジェの戦い」を思わせる展開を選択した作品に「未来少年コナン」「ダロス」等がある。こういったモブ・シーンは、アニメが不得手としている技術のひとつである。
そもそも強大な組織力に対して、強力とはいえ選ばれた戦士数人とか、ロボット数台といった、ゲリラ活動に近い戦力で立ち向かうのには無理がある。そういった拘泥が、粗っぽい画とはいえ、蜿蜒と続く魚の援軍となったに違いない。
しかし、ポセイドン族及び怪人そして怪獣らは、海の生き物にどのような悪行を働いたのだろう。海自体を作り変えようとしたふうには見えない。陸人と同様に、単に収奪していたのではないだろうか。トリトン族は魚や鳥、海獣と会話できるが、それは最初から可能だったのではなく、トリトン族と接触する事で教化されているとすれば、陸人にとってもトリトン族は脅威という事になる。
120◆あらかじめ失われた両親◆
第2話、12話を経て、トリトンは既に両親の死を確信していたはずである。第14話の旅イルカの言葉のような光明があったにせよ…。それに、もし生きているのなら、大西洋に入ったトリトンを足止めするために、人質として使うはずであると。或いは、いっそ消息は謎のままである事を、望んでいたのかもしれない。
ゲルペスは、トリトンが両親を探していると考え、戦意の喪失を狙って(事の真偽とは別に)両親殺しをバラしたのだろう。その結果は火に油。短剣に輝きという仕儀となった。
121◆種の臨界◆
ポセイドン一族の寿命は定かではないが、幼児から老人まで揃っているので不死ではないらしい。アトランティス人による人身御供の内容や、当時の絶滅戦争によって、人口がどの程度まで減少したのかについては、具体的には語られていない。
個体数が極端に減ると、否応なく遺伝子の均一化が進行し、正常な子孫が生まれ難くなる。ポセイドン族は、遺伝子の完全複製と多様性の問題を解決していたのだろうか。
122◆陽はまた昇る◆
オリハルコンの短剣の役割、それは同じオリハルコンで造られたポセイドンの像を破壊する事。破壊とは即ち生なり。海中に隠されたる太陽は、合一によって本来の姿へと還る。それはまた、ポセイドン一族の絶滅を意味する。
表層の神殿を抜け、地下世界への突入から最後の大爆発までも含めて、映画「地底探険」でのアトランティス遺跡のシークエンスに取材している。また、ポセイドン像の破壊光線は「謎の大陸アトランティス」が下地になっているのだろう。
最終話に於いてトリトンは、未必の故意ですらない戦いによって、ポセイドン一族、約一万人を一瞬にして死に追いやる。この結末が、富野監督のその後の作品に、装いを変えながら踏襲されていったのは言を俟たない。
短剣と像、マイナスとプラス・オリハルコンの合一で、短剣は永遠に失われる。いわゆる「剣」が、神の威光の象徴(エクスカリバー、ネイリング、申命記の輝く剣、デルンウィン、バルムンク…等)なのに対し、短剣は直截的には男根の象徴である。
第27話のサブタイトルは、ヘミングウェイ「日はまた昇る」の引用であろう。この作品の登場人物は、戦傷によって性的不能者となっており、(一次)大戦後の虚無の中で新しい価値を探求し、旅を続ける。作品のタイトルは、同作冒頭にある「旧約聖書・コヘレトの言葉1章」からの引用句と登場人物の生き方を絡めたものである。
トリトンの短剣喪失すなわち男根喪失、或いは男性的リビドーの消失は、正義の瓦解が生んだ虚無であり、おそらく、トリトン族という種族そのものへの、忌避感情と同義だろうと思われる。「エルガイム」の最終回ではないが、ポセイドン(ポセイダル)はトリトン族への復讐を果たしたのではないだろうか。しかし、全てを失ったとしても『陽はまた昇る』のだ。
後年、類似のプロットを扱った映画「ダーククリスタル」が、ドサクサに紛れてハッピーエンドだった事と比べると、第27話がいかに冷徹なものかが判る。更に後年のオーソン・スコット・カード「エンダーのゲーム」にその残像を見たような気がした。