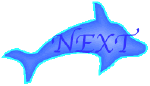「Tの拾遺」は「海のトリトン」全27話の感想集です。 虚実綯い交ぜの解説文も入っています。各話冒頭の呼出しには、左端のローカルメニューから選択して下さい。
以前は世界地図の各ポイントをクリックする選択枝もありましたが、現在はGoogleMapで各地の衛星画像にリンクを貼ってます。
(テキスト作成は1997年)
「海のトリトン」へ至る助走
今や郵便切手にもなってしまった国民的漫画家・手塚治虫は、決して「海のトリトン」を産み出すためだけに登場したわけではない。が、以下えんえんと「海のトリトン」を世界の中心に据えたような雑文が続く事になる(はずである)。
また、原作トリトンとアニメ・トリトンは、物語の根幹から枝葉に至るまで見事に相対する妙な関係にある。しかし、ここではその優劣を考えるわけでもない。これは手塚治虫の天秤において、既に回答が出ているからである。あえて言えば、アニメ版はデファクト・スタンダードである。
◆擬人化のボーダーライン◆
アニメ・トリトンの中で登場する通信クラゲは、毎回出演する使い捨てヤラレ・キャラである。しかし、原作トリトンのクラゲは単なるブービー・トラップに過ぎない。
アニメ版のルーツは手塚治虫自身も参画した東映動画「西遊記」の小竜あたりか。これが海洋生物同士の隠密的コミュニケーションへ変化したのは「空飛ぶゆうれい船」の通信ウミウシだろうか。(同作の脚本は辻真先だが脚本段階では登場していない)
対する原作版のクラゲは「化石島」のナマコの如き擬人化すら全くない。単なる道具である。これは「エンゼルの丘」のイソギンチャクについても同じである。昆虫キャラに対する熱い思い入れとの落差の大きさ=擬人化の境界は何処にあったのか。単に好き嫌いの問題ならば、クモに対しても同様の扱いになったはずである。
この疑問への答えは、BE-PAL誌上に紹介された「治蟲堂・原色増訂ヒドロ蟲類圖譜」及び「原色櫛水母圖譜」にあった。手塚治虫は少年時代に、海洋無脊椎動物の実物を観察する機会に恵まれなかったらしい。すると、ナマコは食用として水揚げされた実物を見る事もあったのだろうか。
アニメ・トリトンに登場する通信クラゲ、アーモン、ガダル、ウミワタといった個性的な無脊椎動物の存在。これらは原作トリトンにとって、形態模写は出来ても感情移入できない、最も遠い存在だったに違いない。
◆熱血少年小説◆
手塚治虫が、作品の独自性について強烈な自負を持っていた事は、生前の手塚本にも散見される。また、作風やジャンルが同じ傾向の漫画家ならば、先輩・後輩を問わずライヴァル視していた事も、つとに有名な話である。
この事から推測できるのは、原作トリトンの解説やあとがきに於けるアニメ・トリトンへの素っ気ないコメントが、まさにアニメ版の伝奇SF性への評価だろうという事だ。そして、手塚治虫に最も影響を与えたであろう戦前戦後冒険小説も、アニメ・トリトンと同じ成因により表面へは浮かび上がってこない。
この事は、海野十三全集・別巻小冊子「手塚治虫は海野十三をどう見ていたか」(島本光昭・著)で正鵠を射た解説がまとめられている。手塚治虫が少年時代に遭遇したであろう作品は、海野十三を筆頭に大佛次郎、高垣眸、佐藤紅緑、野村胡堂、南洋一郎といったそうそうたるライン・アップが想像できる。各々の作品は、手塚治虫の血肉となり様々な形で手塚漫画へ注ぎ込まれたのであろう。海野十三作品だけが「海のトリトン」のルーツではない。しかし、「海底大陸」や「海底都市」など一連の海洋冒険小説がなければ「トリトン」の世界も容易に形成されなかったであろう。
更にもう一段遡及すれば、H. G. ウェルズやJ. ヴェルヌの海洋作品も顔を覗かせているが、これは海野十三の血肉になったのかもしれない。
◆輝く瞳◆
偉大なるオリジナリティ。大きな瞳に光の点が輝く。
夏目房之介・著「手塚治虫はどこにいる」に書かれたパイオニア・手塚治虫の業績のひとつである。ところが芸術新潮誌上で、すでに浮世絵に於いてこれを行なっていた…とこれまた、同じ夏目房之介が書いている。
浮世絵の方は、月岡芳年の一連の作品で、江戸末期から明治初期という「るろうに剣心」な時代である。月岡芳年の作品は、現在の漫画で使われている表現技法総ざらえの感があり、正しく原点だろうと思われる。三島由紀夫、江戸川乱歩、谷崎潤一郎、芥川龍之介ら近代文学者も贔屓にしていたらしいので、手塚治虫も目にする機会はあったのではないだろうか。
そもそも、瞳に光の点という鑑賞者を見返してくる視線は、西洋絵画の技法なのだ。画家、絵師、漫画家、動画家…たゆまぬ観察によって、より印象的な表現を求めていけば、最後は効果的な記号のチョイスとその組み合わせに収束される。それこそが、オリジナリティではないか。
手塚治虫は、映画的手法を漫画に導入した、というのが巷の評価である。それも間違いではないが、月岡芳年の作品を眺めていると、決してそれだけではないと思える。
◆原作トリトン◆
海の物語のほとんどは、人魚を扱った作品のように思われる。たぶん例外もあるのだろうが確認できなかった。
「化石島」→「ピピちゃん」→(「リボンの騎士」)→「エンゼルの丘」→「ロビンちゃん」→(「孔雀貝」)→「青いトリトン」…。
これらを読み比べると「トリトン」が異質に感じられる。原作トリトンが、竹内オサム「手塚治虫論」に言う所の海洋版「ジャングル大帝」の態を成している為であろうか。
各国の人魚説話を核にした親・子・孫の三代に渡る年代記。そして、「子」にあたる者・物語の主人公の死によって完結する世界である。三代というのは、「拓く・耕す・穫る」農耕文明の基本みたいであるが、数字への嗜好もありそうなのでここでは詮じない。気になるのは、海と人間の関わり方である。
ポセイドンは人間と取引し経済・資材面で互いに噛み合っている。トリトンは義母・義兄と周辺社会との接点を持っている。人間にとって、ポセイドンはフランケンシュタインの怪物である。さしずめトリトンは、ジミー・クリケットか。(するとガノモスは妖精の女王さまか)
手塚治虫が描いたポセイドンのエピグラムは明確である。また、後半にトリトンが、アジュールであった陸を水びたしにするエピグラムもはっきりしている。しかし、ポセイドンとトリトンにとって、陸との接触は全く必要がない。陸を征服するにしても、大津波と地震と超低気圧の連発で充分ではないか。海と陸の関わりが深くなると、余計なものが視野に入り物語はそのぶん重くなりリスクを背負う。しかし、リスクが増した割に背負ったものの必然性・切迫感は乏しい。
物語の終息とエピグラムの発信、そんなもののために死んでいくトリトンが無惨なだけであった。
◆解体と創造◆
原作トリトンからパイロット・フィルム「青いトリトン」の製作。そして、TVアニメ「海のトリトン」の放映。
この後、原作トリトンは「青いトリトン」から「海のトリトン」へ改題される事になる。原作トリトンは発行順に、産経新聞連載版、単行本向け編集改訂版、連載復元版、連載復元版の検閲更訂版が存在している。それぞれに多少の変化はあるが、原作トリトンに於いて不変なのは、大衆向けの作劇方法である。主人公の死と機械仕掛けの神によるプロット転換がそれだ。
大衆向けである事について、俗っぽいと批判するのは簡単だ。また、肯定するのも容易い。この方法は大衆小説や探偵小説に使われる、正しく一般受けするものだからだ。
アニメ・トリトンに対して、手塚治虫は一切関わっていないとコメントする。それは当然だろう。ここぞとばかりに用意しておいた「神」や「聖母マリア」を、いざ出す段になって現場監督がこれをキャンセルしたら大喧嘩になるに違いない。
原作とアニメ版は相対する関係であるが、末節の詳細部分のみを見るとアニメ版は原作を踏襲している。導入部のクラクラするようなケイビングや作品世界をカスタマイズせずに、飽くまでSFに留まろうとする姿勢など実に忠実である。これが原作者への敬意もしくは方便かは判断がつきかねるが…。原作に登場しない挿話は、TV放映に伴って多量のスクリプトが必要なためであって、これは当然と考えるべきだろう。
徹頭徹尾、大衆向けとして完結した原作トリトン。アリストテレス「詩学」の教えに従って、ストーリーの中で完結させたアニメ・トリトン。虫プロという接点を介して相反する、製作者たちの理念のおかげで、ファンはこの二つを比べて見る事が出来るのだ。